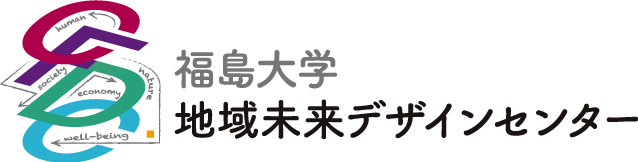プロジェクト
いのちを守る防災減災プロジェクト
地域未来デザインセンター 特任准教授 藤室 玲治
人間発達文化学類 特任教授 天野 和彦
実施期間:2024年~2026年
災害が発生する前に備えておく意味での防災・減災については、さまざまな分野で進められおり、モノや避難手順等の意識は高まってきている。
しかし、災害による直接死に対する働きかけとは別に、発災後、避難所等の生活の中で失われていく命、「亡くならなくてもいい命」に対する働きかけが急務とされている。
「いのちを守るため」に必要な「考え方」や正解のない問題に対峙する考え方を普及させることも、防災・減災の一部として重要な部分である。
そのために必要な人材育成、啓蒙、場づくりが必要であるため、さすけなぶる研究会を軸とする3ヵ年のプロジェクトを実施している。